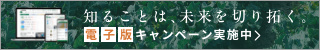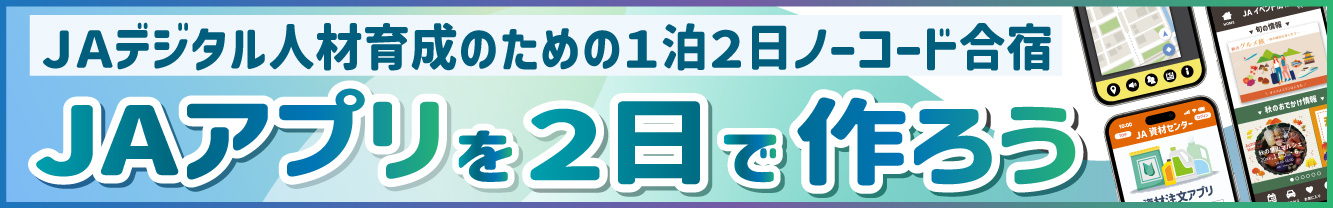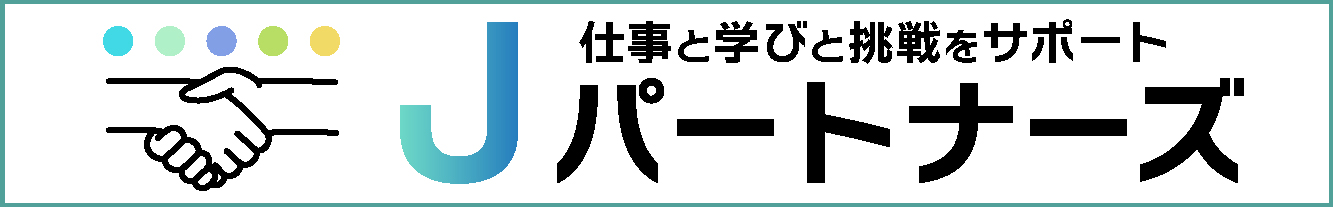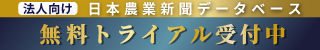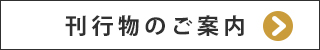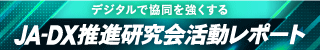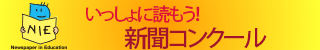[論説]日米関税交渉への懸念 米の譲歩は許されない
先週行われた日米関税交渉で、米国が協議の土台に乗せたのは、米通商代表部(USTR)が3月末にまとめた「外国貿易障壁報告書」。非関税障壁の筆頭に米を挙げて問題視し「700%の関税をかけている」と主張した。これに対し、江藤拓農相は会見で算定の根拠について「理解不能だ」と述べたが、米の一層の市場開放を求める米国側の姿勢は変わらない。根拠のない要求に対し、日本は毅然(きぜん)と反論すべきだ。
日米両国は、2016年に署名した環太平洋連携協定(TPP)12の際、売買同時入札(SBS)方式で、米国の輸入枠を最終的に7万トンまで新設することで合意した。17年、第1次トランプ政権で米国がTPPから離脱し、米国枠の設置は見送られた。だが、USAライス連合会は18年、TPPで同意した7万トンの水準は「不十分」とし、15万トン程度への拡大を要望した。
米国は長年、日本の米市場開放を虎視眈々(たんたん)と狙ってきた経緯がある。赤沢亮正経済再生相は交渉後、「大事なのは全体のパッケージだ。お互い納得できるかということで、ウィンウィンの関係をつくっていく」と述べたが、SBSの拡大や1キロ341円という民間貿易の関税を下げるようなことがあってはならない。輸入を増やせば増やすほど日本の農業農村は衰退し、食料・農業・農村基本計画が掲げる45%の食料自給率達成は遠のく。
自動車は日本経済を支える重要な産業だ。だが、工業製品のために農畜産物を犠牲にする通商交渉はもうやめてもらいたい。日本の農産物貿易は圧倒的に輸入超過であり、米国から毎年、家畜飼料向けのトウモロコシや大豆などを大量に輸入している。輸入米の半数近くは米国産だ。自動車による貿易不均衡は自動車分野で対処するのが筋だ。
石破茂首相は19日夜、林芳正官房長官や赤沢担当相らを集めて協議した。日本は米国に対し優先順位を付けてほしいと求めているが、米や牛肉など農畜産物の輸入拡大はこれ以上、認められないという強い姿勢を貫いてもらいたい。
世界に先駆け、日本は再度、月内に米国との交渉に臨む。相互関税などで日本を揺さぶる米国にどう対峙(たいじ)するのか。農業、農村を大事にする石破政権の粘り強い交渉力を発揮する時だ。
 Line
Line