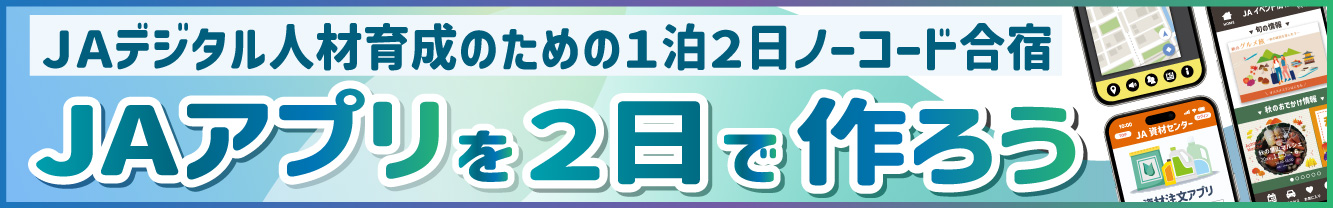お探しの記事が見つかりません
- アクセスしようとしたファイルが見つかりません。
- URLアドレスが間違っている可能性があります。
- 指定された記事が削除された可能性があります。
- 日本農業新聞公式ウェブサイトに掲載された過去1年分の記事を検索できます。
- (※他社提供の記事、著作権により掲載ができないものは掲載していません。)
日本農業新聞からのお知らせ
-
6/16 令和7年度「農を語れる職員塾」第1回 申し込み受付中
-
第2回学生写真コンテスト/第51回読者の写真コンテスト 作品募集
-
日本農業新聞が実施した、令和5年補正 果樹農業強靭化緊急対策「花粉供給緊急対策事業」の事業報告書を公開しました。
-
JAアプリを2日で作ろう! ~1泊2日のJAデジタル人材育成のためのノーコード合宿~
-
個人情報利用目的の公表・保有個人データに関する事項の周知について 更新しました
-
工藤阿須加さんが当社公式アンバサダー就任!2月から工藤さん出演テレビCM「知ることは、未来を切り拓く。」編を放送開始。
-
【電子版が月額1,100円】新規就農者応援キャンペーン実施中
-
学生は日本農業新聞電子版が半額以下!「学割キャンペーン」6/20まで
-
日本農業新聞電子版がアプリでさらに便利に! 「日本農業新聞ニュースアプリ」
-
JAの業務効率化をデジタルで支援「Jパートナーズ」/生成AI「金次郎」に新機能、議事録・校正モードを追加
-
【賞金10万円】「令和6年度記事活用エピソード」エピソード募集のご案内
-
購読料改定のお願い
-
持続可能な農業を推進 「みどりGXラボ」会員を募集!
-
老眼、弱視などに対応した機能を実装/日本農業新聞公式ウェブサイト ~障害や年齢に関わらず全ての人が平等に情報にアクセスできるウェブサイトを目指します~
-
みどりGX新聞を創刊しました
-
【11/1から】全国の地方版が、日本農業新聞電子版で読めるようになりました!
-
【インボイス制度】電子版、または併読の購読料の領収書発行について
-
JA-DX推進研究会エントリー受付中
-
日本農業新聞電子版のご案内
-
デジタルメディア「和牛新聞」創刊
プレスリリース

-
-
野菜高騰でも“おいしさ”で選ばれるミニトマトが躍進 和歌山発のブランド「こくつよ みにとまと」の挑戦農業総研
2025年5月9日 掲載 -
【業界初・注目自治体が登壇】農業×官民連携の“稼ぐ仕組み”を徹底解剖!アグリコネクト株式会社
2025年5月9日 掲載 -
農地をもっと効率的に「農地集約プログラム」参加市町村を募集東北学院大学 黒阪研究室
2025年5月9日 掲載 -
「畜産ジョブフェスタ」札幌会場、大盛況で開催!株式会社TYL
2025年5月9日 掲載 -
【福岡・直方市】40品種を食べ比べ!ブルーベリー狩りが6月7日スタート|完全予約制でゆったり体験株式会社アグリハニー
2025年5月9日 掲載 -
【TGI フライデーズ】世界で一番ハッピーな「ありがとう」を。母の日は、フライデーズで!ワタミ株式会社
2025年5月8日 掲載 -
【PFUブルーキャッツ石川かほく】石川県内灘町にて復興田植えを実施PFUブルーキャッツ石川かほく
2025年5月8日 掲載 -
大人気商品が今年も期間限定で登場!「旬を味わうサラダ 青じそミックス」株式会社サラダクラブ
2025年5月8日 掲載 -
広がる持続可能な食と農の輪/「みどりGXラボ」会員1000人、「みどりGX新聞」読者3000人を突破!/日本農業新聞株式会社日本農業新聞
2025年5月8日 掲載 -
Farmnote Gene、ゲノム検査市場で国内シェアNo.1に株式会社ファームノート
2025年5月8日 掲載
-
-
-
北海道立北の森づくり専門学院2025「オープンキャンパス」「学院説明会」開催北海道
2025年4月30日 掲載 -
木材製品のCO2排出量をサプライチェーンで可視化する!岐阜県「白川LSC」が取り組む、木材の環境性能に対して責任ある行動。東濃ひのき製品流通協同組合
2025年4月30日 掲載 -
秩父湯元 武甲温泉が、「第75回全国植樹祭」の応援企画を開催。お風呂に埼玉県産の木材を使用した「木製地球儀」のモチーフを浮かべます株式会社温泉道場
2025年4月25日 掲載 -
ベトナム市場調査レポート販売|ベトナムにおける植林事業展開に関する法規定ONE-VALUE株式会社
2025年4月21日 掲載 -
【京都府初】官民連携!循環型森林整備の推進に関する協定を締結京都府福知山市
2025年4月10日 掲載 -
トルビズオン、福岡県添田町にて4社連携により、4tの林業資材をDJI FlyCart30で空輸トルビズオン
2025年4月8日 掲載 -
ステラーグリーン、西湘フォレスト、森林再生システムがカーボンニュートラルの実現に向けパートナーシップ協定を締結SBプレイヤーズ株式会社
2025年3月28日 掲載 -
Archeda、自然由来カーボンクレジットのプロジェクトを定期的にモニタリングするソリューション「Green Insight Monitoring for MRV」を提供開始株式会社Archeda
2025年3月26日 掲載 -
どんぐりを育て、山へ植林。「戻り苗」が東京でも始動。株式会社ソマノベース
2025年3月18日 掲載 -
岡田圭右・ゆいちゃみも思わず「住みたい!!」 “日本一東京に近い田舎”の魅力とは!?ニッポンの村・町自慢の好評シリーズ第8弾!テレビ大阪株式会社
2025年2月27日 掲載
-
-
-
円安で輸入水産物の値上がり目立つ 輸出は不漁や中国禁輸で伸び悩み 主要商材の2024年貿易動向を水産専門記者が解説株式会社みなと山口合同新聞社
2025年5月9日 掲載 -
ホシザキ初の床置型真空包装機を発売ホシザキ株式会社
2025年5月8日 掲載 -
北海道・木育(もくいく)フェスタ2025 第75回北海道植樹祭の開催北海道
2025年5月8日 掲載 -
『Discover Japan(ディスカバー・ジャパン)』 2025年6月号「人生100年時代、食を考える。」が5月7日に発売!株式会社ディスカバー・ジャパン
2025年5月7日 掲載 -
日米の知恵で持続可能な水産へ!セミナー「気候変動のもとでの資源管理と評価の在り方を考える」一般財団法人EDFジャパン
2025年5月2日 掲載 -
ベトナム市場調査レポート販売|ベトナムの水産加工業界と今後の展望ONE-VALUE株式会社
2025年5月2日 掲載 -
高性能かつ手頃な価格を実現した水中測量機器シリーズ、JOHNANが日本国内販売を予定JOHNAN株式会社
2025年5月1日 掲載 -
豪州版「はぐくむたね(R)」を用いたウニ陸上養殖試験をディーキン大学と共同で開始株式会社北三陸ファクトリー
2025年4月30日 掲載 -
【本日スタート!】大阪・関西万博「宴~UTAGE~パビリオン」1Fにて、“伝助炙り煮穴子重”を期間限定販売株式会社ファイン・プランニング
2025年4月28日 掲載 -
デンマーク国王訪日レポート:オカムラ食品工業とMusholmが養殖増産に関する協定書に調印、青森サーモン(R)ほか商品を、デンマーク大使館でのレセプションにて出品!株式会社オカムラ食品工業
2025年4月28日 掲載
-
-
-
円安で輸入水産物の値上がり目立つ 輸出は不漁や中国禁輸で伸び悩み 主要商材の2024年貿易動向を水産専門記者が解説株式会社みなと山口合同新聞社
2025年5月9日 掲載 -
野菜高騰でも“おいしさ”で選ばれるミニトマトが躍進 和歌山発のブランド「こくつよ みにとまと」の挑戦農業総研
2025年5月9日 掲載 -
【業界初・注目自治体が登壇】農業×官民連携の“稼ぐ仕組み”を徹底解剖!アグリコネクト株式会社
2025年5月9日 掲載 -
農地をもっと効率的に「農地集約プログラム」参加市町村を募集東北学院大学 黒阪研究室
2025年5月9日 掲載 -
「畜産ジョブフェスタ」札幌会場、大盛況で開催!株式会社TYL
2025年5月9日 掲載 -
【福岡・直方市】40品種を食べ比べ!ブルーベリー狩りが6月7日スタート|完全予約制でゆったり体験株式会社アグリハニー
2025年5月9日 掲載 -
【TGI フライデーズ】世界で一番ハッピーな「ありがとう」を。母の日は、フライデーズで!ワタミ株式会社
2025年5月8日 掲載 -
【PFUブルーキャッツ石川かほく】石川県内灘町にて復興田植えを実施PFUブルーキャッツ石川かほく
2025年5月8日 掲載 -
大人気商品が今年も期間限定で登場!「旬を味わうサラダ 青じそミックス」株式会社サラダクラブ
2025年5月8日 掲載 -
広がる持続可能な食と農の輪/「みどりGXラボ」会員1000人、「みどりGX新聞」読者3000人を突破!/日本農業新聞株式会社日本農業新聞
2025年5月8日 掲載
-
e農サーチ

関連サイト
-
日本農業新聞 広告サイト
-
海外農業研修視察団
-
日農カルチャーオンライン
-
音声配信「聞く農」
-
特設サイト「農家の特報班」
-
The Japan Agri News(英字版ニュース)
-
netアグリ市況
-
アグリライターST(ID・パスワードが必要です)
-
「アナザー・スタッフ」
-
直売所情報誌「フレ マルシェ」
-
(株)JA情報サービス
-
公式エックス「日本農業新聞」
-
公式エックス「農家の特報班」
-
公式エックス「日本農業新聞 AD_TALK」
-
公式インスタグラム「日本農業新聞」
-
公式YouTubeチャンネル「日本農業新聞」
-
公式フェイスブック「日本農業新聞 若者力」
-
日農カルチャーオンライン公式インスタグラム「nichino_culture_online」