「孤独のグルメ」では今までも、全ての店で「いただきます」を言ってきた。言わなかったことは1度もない。
目の前に出された料理をいただくという姿勢は、アジアにも誇れる食文化の一つだと僕は思います。だからアジアで支持されている日本の食は、そこに共感をいただいているんじゃないかな。
農家が自信を持って愛情を込めて、食べる方に届けた野菜や米。農家が育てた野菜は、最終的に誰かの口の中に入り、誰かの身になる。そこに僕らも感謝の気持ちで、作った人に対して手を合わせる。日本の食文化は、海外からも憧れられている。いまだに長寿の国でいられるのは、生産者ら作り手の努力のおかげだと思います。
□ □
「孤独のグルメ」はいろんな人に見ていただいています。例えば、断食中のお坊さん。断食している時に 満腹感を味わうのか、勇気をもらうのかはわからないですが、いろんな楽しみ方があるんだな。ご主人を早く亡くされたおばあちゃんが亡き旦那さんと一緒に食べている気持ちで見るとか、子どもが偏食をなくすために見ているとか。とても客層が幅広い。作っている僕らは、そこまで想定していなかったから、思わぬ効果に驚いています。僕としては、そういう食べ方をしてみんなを元気づけようという気持ちでやってるわけじゃない。ただ単純に腹減った、おいしいから食べるっていう、その基本はぶれてない。
それを12年も支持していただき作品を作り続けられることは光栄。ただ、本当の本心、本意はわからない、作っていながらも本心はわからない、謎に包まれている。
□ □
映画を作るきっかけがコロナ。コロナで撮影が止まり、コロナ後の日常もマスクをして、飲食店でもついたてがあるという時代があり、飲食店が非常に苦境に立たされた。今まで世話になった飲食店の人たちが、どこか元気になれるような作品を作るという使命感が、僕らには間違いなくありました。だから飲食店を再生するストーリーは、もう根底に主旋律として当然入れるべきだと思っていたし、そこにできればラブストーリーを入れたいと思っていた。テレビシリーズはただ「腹減った」、そして店を探すという流れですが、映画は輸入雑貨商をやっている(主人公の)井之頭五郎が職業を利用して海外を渡り歩く。日本に帰ることが叶わなくなったお年寄りと会い、「(子どものころに味わった)スープを飲みたい」と頼まれる。
記憶の中のご馳走を、なんとかもう1回自分で味わうことができないだろうかというストーリーは、いろんな人が共感できる。そのスープを探すことによって、今は失われてしまったファストフードじゃなくて、ちゃんと出汁を取って、生産者から台所に渡っていく。そして家庭で手間暇をかけて、愛情を込めて作られたものを求めるという流れを副旋律として描きたかった。その二つがメロディーとして映画の中で奏でられればという思いが1番大きい。
映画に登場する韓国の島は、どこかユートピアみたいな地。ああいう地で本当に安心な食材を、できるだけコストをかけずに作っている。そんな楽園があったらいいだろうなと思った。そして韓国の島で日本の女性も一緒に暮らしている。そこの料理は、フードコーディネーターの方に作ってもらったフィクションの料理なんですけど、そこは本当に究極のファンタジーとしておいしいもの、日本と韓国の知恵を織り混ぜた最高のご馳走を食べるシーンにしたかったんですね。
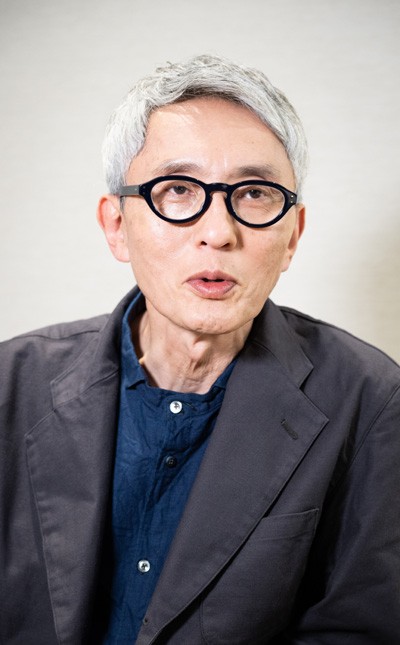
だから音楽もだいぶ変えた。基本的にピアノがメインになっていて、女優の内田有紀さんが演じる女性の気持ちの流れを音楽でみせた。後半はピアノの単音で奏でていきながら、女性の気持ちが動いたところでメロディーラインが入り、離れて暮らしている旦那に届くというラブストーリーを1番映画でやりたかった。そこはものすごく丁寧に、音の入れ方も含めて作らせていただきました。
本当に食べ物は、ここに出されている瞬間だけじゃなくて、例えばこのダイコンをどういう人たちが育てて種をまいて収穫して、誰が運んで持ってきたものなのかまでが、ちゃんと物語になっているということをわかってほしいなと思った。
ある島で女性たちが、その食べ物を育てて、魚を取って海藻を取って、それで自分たちでおいしいものを作っている。ああいう地があったらみんな行きたいなって思うような、全てにおいて責任を負ってる人たちが僕らの口に入れるものを考えてくれているっていうことが僕にとっては理想。農家や農業に携わっている方も、やっぱりそういう責任を持っている調理人に農作物を渡したいだろうし、それをきちんと分かった人に食べていただきたいと思っている。
種を撒くところから、その前には土を育てることから物語は始まっている。この種をまいて、この人に野菜を作ってもらって、それをおいしいって食べる人がいるというのがストーリー。その文脈をきちんと描くことが映画でもやりたかったこと。そこを農家や農業に携わっている人も見て感じてほしい。そして食べる人まで意識をつなげてほしい。
映画の畑の景色は三浦半島。アメリカ人の俳優が、広い農地で自分で無農薬で野菜を育てて、ハチミツを取ったりもする。彼の畑で撮影をしたかった。
アメリカ人なんですけど、日本の風土と土地を愛している。その彼の畑で撮影し、とにかく雑草まみれの畑に旬の野菜がある。その畑で採れた野菜を実際に映画でも使わせてもらいました。
農家との直接の交流は、今はなくなりましたね。農家とすごくつながっている八百屋さんが店を畳んでしまい、ちょっと今、悲しい状況ですね。
本当は、できればその作っている人の顔が見える野菜や米を家でも使いたいなと思っている。そういうのは食べていても本当に自分の実になるなっていう気がする。
□ □
日本農業新聞は購読していませんが、新聞3紙を購読しています。今インターネットの情報があふれている。誰が書いたものかもわからない情報に惑わされるという時代になってしまった。でも新聞は、新聞社の方がいろんなチェック機関を通した上で、ちゃんとした記事として手元に届けてくれる。その安心感っていうのは絶対なくすべきじゃないと思うんですよ。だから、新聞はもう僕は絶対に死ぬまで取り続けようと思って。だから、本当に新聞から得られることっていうのは、僕にとっては大きい。そして、あらゆるジャンルで、日本人はその失われた30年を経て、いろんなところに自信を失ってしまった。安易な道に行かずに、きちんともう1回努力を1から構築して物づくりに励むことが大切だ。農業もそうだし、僕らのエンタメも間違いなくそうだと思う。丁寧にやり続ければ絶対においしいスープができるという、これはもう間違いのないことだと思う。だから、もう1回、自分たちの自信を取り戻すためには、基本をもう一度おさらいして、丁寧に丁寧に仕事をすることに尽きると思うんですね。それが、ロックな生き方だ。
ただ、転落することはあっという間、一瞬でもある。とにかくどの産業も努力し続けないと、10年後、20年後の未来はないとも思う。
(聞き手・岡田健治、尾原浩子)
 Line
Line















