世界中に平和を訴求する団体がある中で、受賞を聞いて「夢みたいだ」と思って、思わず頬をつねった。
広島市役所で吉報を聞いた。実は、10年くらいになるのか、毎年、ノーベル平和賞の受賞者を発表する時は記者会見をセットして、待っている。内心では今年も受賞しないと思っていた。イスラエルのガザで血まみれの子どもたちを救おうとするような団体が受賞するのではないかと予測していたので、まさか被団協が受賞するなんて思わなかった。本当に驚いた。「夢か、本当か、マジか」と口走ったほどだ。
1945年、8月6日。広島に疎開していた私は当時、3歳だった。被爆して逃げて来られたであろうぼろぼろの服を着た女性が、母に、缶詰を渡して「開けてくれ」と頼んだ光景を覚えている。
そして原爆投下の翌日、広島駅の近くで働いていた父親を探しに母と弟と市の中心部に行き、そこで被爆した。丸焼けの地を3日間歩いた。自宅に帰ると父は戻っていた。父は地下にいて死なずにすんだ。もっと原爆のこと、平和のこと、戦争のことを父から聞いておけば良かったと今から思う。自分だけ命が助かったことにためらいがあったのか、父は何も語らなかった。
あの原爆投下から、来年で80年になる。80年の節目を前にしてノーベル賞の受賞となった。「核と人類は共存できない」という言葉を残した広島県被団協の初代理事長、故・森瀧市郎さん、核廃絶に向けて「ネバーギブアップ」と戦った故・坪井直さんら大先輩がいたからこその受賞だ。偉大な先輩方に、受賞を報告した時はこみ上げるものがあった。
□ □
私が大切にしてきたのは若い世代との交流。これまで数多くの地に呼んでいただき、被爆体験を証言してきた。高校生や子どもたちに、映像や紙芝居、プロジェクターなどを使って説明する。若い人とどうやって平和を広められるか話し合う。小学生5人しかいない奈良の過疎地、北海道・帯広や山口の山陽小野田市など、全国各地に思い出深い交流がある。定期的に訪問する広島県内の高校もある。若い世代ともこの受賞を喜び合えたことに、感激している。被爆者は10万4000人。あと10年したら証言できる人はほぼいなくなるだろう。だから被爆2世、3世、そして若い人にどれだけ伝えられるかが鍵なのだと思う。広島平和記念資料館を訪れて、血まみれになった子どもたちの姿を写真で見て、被爆者の熱心な語りを聞いたら、戦争を実体験としては知らない若い世代でも、必ず伝わるものがあると信じている。
戦争は、子どもや働き盛りの若者を犠牲にする。戦争を仕向ける権力者は戦地に行かない。そこに戦争の恐ろしさがある。若い世代と平和、戦争、核のことを共有していかなければならない。
大人や権力者たちに言いたい。目の前の子どもが犠牲になることを想像し、日本が有事になった時にひとりでも多くの人が「戦争反対」と声をあげてほしい。戦争は絶対にだめだ。

私は過疎化も高齢化も甚だしく進む北広島町で米やソバを栽培している。
戦後、小学校に上がる時に父親の実家である豊平町(現在の北広島町)に来た。5人家族で貧乏な生活。牛で田んぼをすいて、手作業で田植えも稲刈りもした。父は日雇いの土木作業、母は農業で生計をたてた。私は小学生の頃から家族のご飯を作った。
小学校5年生、高熱にうなされる日々が続き半年間近く、学校を休んだ。今思うにあれは原爆症独特の病だったように思う。病院の先生が「米国から輸入されたストレプトマイシンという注射があるが打ってみますか。注射代はすごく高いですよ」というような話を母に伝え、母は私が助かるならと注射代を払ってくれた。それで少しずつ元に戻った。今思うと、もしかしたら私もあの白血病で亡くなった佐々木禎子さんのような運命をたどったかもしれないと思う。
定時制の高校には春は材木、秋は稲刈りなど農作業、冬は牛の爪切りと働きながら通った。
定時制高校を卒業して、鋳物工場へ就職し働いた。寮生活で土曜日の夕方には自宅へ帰り、農作業の手伝いをした。私の左手には指がない。貧乏だったので、必死で人の倍働かなければ生きていけないと思って働いていた中で、工場の事故に遭った。もうだめかと思ったが、左手だったということもあり、なんとか生活できている。左手の指を失っても、営農を続けてきた。
頼まれて町の議員になったこともあるが、私には政治家は向いていないと思っていた。
農家という背景が影響しているのか、私は食べることと平和はつながっていると心から思う。農機も肥料も高騰し、農業で生計を立ててこの山間部で生きていくことが難しくなっている。産業、地域の基盤がしっかりしていることは社会の基本だろう。政治家にその基本を大切にしてほしいと言いたい。
かつて若者は街へ街へと向かった。日本社会は石油コンビナートなど工業化を追い求めた。一方で公害や環境汚染の問題も発生した。
今は若者が都市へと向かう一方通行ではない。それは昔のような生活に戻っているということではない。日本の山間部、田舎は電気も水道も不自由がなくなった。平和だから農村でも都市でも支え合って生きていくことができる。平和だからこそ、農業という産業が確立されている。
戦争になれば、市民は飢えにもがき苦しむ。米一粒のありがたみを戦争体験者は誰もが口にする。だから、よく考えると、一粒の米が平和につながっている。そして食料の安全保障と平和、そして農村は地続きにつながっている。昔は稲もみ一つでも取りこぼさず稲刈りをしていた。米は貴重な貴重な食べ物だった。一粒の米を大切にするという思いが、命の尊さや食料の大切さに結びつくのではないか。食料安全保障は、日々の暮らし、日常の農の営みの延長にあると思う。
□ □
被団協の3人の代表委員のうち、ひとりが私。郡部にいる被爆者はほとんどが農家と思う。農家にも被団協や核兵器の廃絶という信念に向かい、被団協の活動に協力してほしいとお願いしたい。被爆者の人数が減っている。みな高齢になり、亡くなったり施設に入ったりという人が大半だ。とても寂しい。高齢化で被団協としての力は衰えているのが現実だ。ノーベル平和賞を受賞する前は、被団協で行動しても報道するテレビや新聞も少なくなっていた。しかし受賞後は、報道機関の取材が殺到していて本当に疲れるという本音も感じている。被爆者は年をとるが、平和に終わりはない。息長く、報道することを報道機関の皆さんにもっと考えてほしい。そして、平和への訴求は今の世でますます重要になることをもっと世の中の人々に知ってほしい。
イスラエル組織とハマスの戦闘が続くガザやロシアのウクライナ侵攻など、世界中で子どもたちが犠牲になっている。血と涙を流している。日本は無関心でいてはならない。
ノーベル平和賞はゴールではない。ここからが、核廃絶、平和に向かってのスタートだ。その意味は被爆者にとってだけではなく、社会全体にとってのスタートになることを願う。
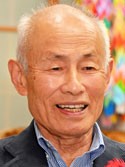 みまき・ともゆき
みまき・ともゆき1942年3月、東京都板橋区生まれ。北広島町で米やソバなどを栽培する。45年3月に東京大空襲に遭い、45年5月に父の故郷である広島に疎開。鋳物工場などで働き、57歳から14年間町議などを務めた。被爆者としての活動は2005年から積極的に始めた。21年に広島県被団協理事長、22年に日本被団協代表委員に就任した。日本被団協の代表委員3人のうちの1人。
 Line
Line














