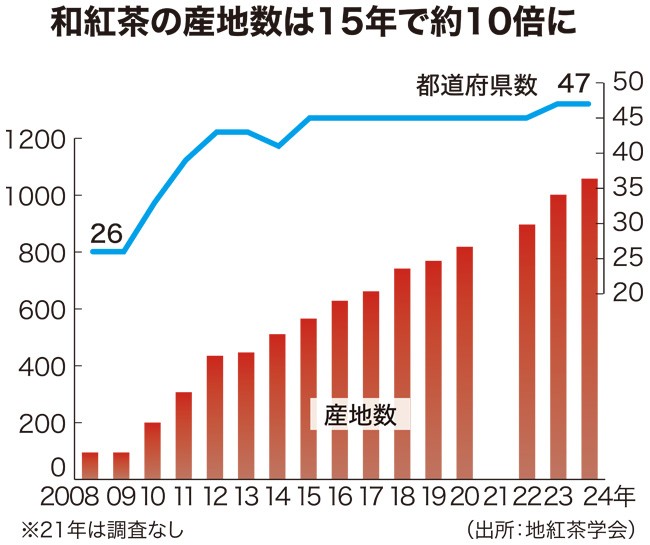
地紅茶学会事務局の藤原一輝さん(70)は「和紅茶の発展はこれからだ。乾燥したミカンの皮とブレンドするなど商品開発の幅が広い。地域の新たな特産品を作ろうと20~30代の生産者が続々と参入している」と話す。
20年農林業センサスによると、都道府県別の茶の栽培経営体数は静岡、鹿児島、福岡、三重、京都の順に多い。一方、紅茶の産地数は静岡が239カ所で全国トップだが、埼玉が100カ所で2番目に多かった。その他、鹿児島95、熊本58、京都46カ所などと続く。
埼玉県茶業研究所によると、高値がつく一番茶は緑茶に、二番茶は紅茶にする生産者が県内で増えている。国内で流通する紅茶のほとんどは輸入品で、国産品は高い付加価値がある。二番茶以降を紅茶に切り替えると、収入増を狙えるという。
埼玉県の紅茶生産者らで作る、さやま紅茶連絡会によると、埼玉県では、個人で製茶工場を持ち、販売までする生産者が多い。同会の比留間嘉章会長は「新たな二番茶の可能性として、紅茶を作る人が増えた」と話す。

緑茶に比べ肥培管理も楽だという。アミノ酸が少ない方がおいしい紅茶ができるとされ、窒素の施肥量を減らせるからだ。比留間会長は、肥料が高騰する中で「生産者が取り組みやすい」とみる。
(後藤真唯子、佐野太一)
 Line
Line















