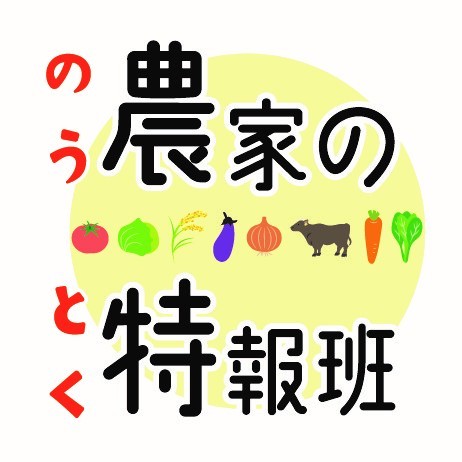
「つぼみが膨らんでつるっとしている。通常だと、こうはならない」。連絡をくれた40代男性農家は木から垂れた花穂を指差し、そう説明してくれた。
ただ、取材時のつぼみは2、3ミリと非常に小さい。目を凝らしたが、記者の目にはよく分からなかった。農家が切り落とした花穂を手に取り、間近で観察すると、ようやく形状の違いが分かった。
正常なつぼみは軸から先端にかけて複数の筋が入り細長い形状。一方、農家が「異常なつぼみ」とする方は、そうした筋がなく、より丸みを帯びていた。

つぼみから未開花症の兆候が見られることは、農研機構が2月に開いた果樹茶業研究会でも報告されていた。
現場での取材後、記者は農家の許可を得た上で、現場で撮影した一部写真を同機構に提供。複数の専門家に確認してもらったところ、農家の見立て通り「(筋がないつぼみは)未開花症に見える」との回答を得た。
記者が訪れた樹園地には、シャインの成木が40本並んでいたが、この農家は「ほとんどの木でつぼみに異常が出ている」と話す。初めて発生した2022年から広範囲での発生が続いている。出口の見えない現状に、別の緑系ブドウへの植え替えも頭によぎっている。
房の形を整える「花穂整形」で症状が出にくい部位を残すなど、できる限りの対応策も取っているが、花穂全体に症状が及んでいると販売できる品質の房を作るのは難しい。「品質の低い房しかできないと分かっているのに、管理を続けるのは徒労感がある」と打ち明ける。
「栽培方法が悪いのか」と自らを責めてしまい、「夜も眠れないことがある」という。
具体的に農業経営にどのような打撃が出ているのか。このまま事態が改善しなければ客が離れ、経営の根幹が揺らぐ恐れがある実態が見えてきた。
シャインを含むブドウ1ヘクタールを栽培し、販路は自ら設けた店舗での直売。ただ、未開花症の発生後、店で求められる贈答向けの形が整ったシャインは「ほとんど確保できない」。他の品種でもわずかながら同様の症状が見つかっているという。

未開花症の対策が確立され、症状が収まって再び売れるようになったとしても、「その時、お客さんは戻ってきてくれるだろうか」と気をもむ。
未開花症を巡っては、昨年に農水省が迅速な対処が必要な「緊急対応課題」に設定した。農研機構と主産5県のグループが発生要因の究明に当たった。ただ、研究は難航し、原因の特定には至っていない。
<ことば>未開花症
5、6月の開花時期になっても、雌しべと雄しべを覆うキャップ状の「花冠」が外れず、果粒が正常に肥大しない障害。原因不明で、農研機構が発生要因の研究を進めている。
皆さんの地域でも、「シャインマスカット」の未開花症が発生していませんか。QRコードから友だち登録をして、未開花症の情報や写真、記事の感想をお寄せください。

■SNSも更新中
▶公式X
■これまでの「のうとく」
▶記事一覧へ
 Line
Line















