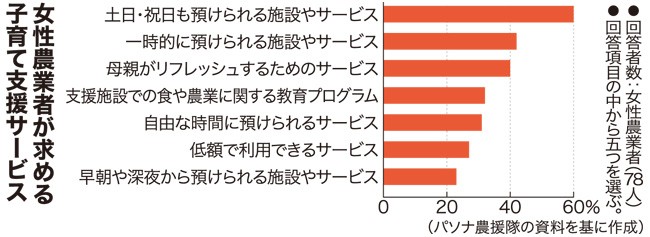
4人の育児奮闘

就農4年目の矢野さんは、農村社会ならではの特徴を子育てに生かす。夫が将来的に水稲で就農を目指していたことから、同市へ2019年に移住。行政のサポートや子育てに理解のある地域住民に囲まれ、農業と育児を両立させる。
農繁期を中心に、作業時間が足りなくなると活用するのが、同市の「ファミリー・サポート・センター事業」だ。事業に登録する会員同士で助け合い、預かり保育や保育園の送り迎えなど幅広く対応する。ママ友達2人と登録し、互いに協力する。日中預かりの負担料金は土・日曜、祝日を含め、1時間当たり300~350円。生後6カ月から小学校6年生まで預けられる。矢野さんは多い月で20時間以上利用する。
産地で「預かり」
放課後の小学生を預かる「子ども教室」を農繁期に開校し、温州ミカン産地を支えるのが愛媛県八幡浜市だ。子どもを持つ地元生産者から要望が高く、家族総出で収穫に励む繁忙期(10~12月)限定で開く。
子ども教室は、早生ミカンの生産者が多くいる川上地区と真穴地区で開く。小学生の児童が対象で、午後2時半から午後6時まで預かる。昨年度は低学年の児童を中心に川上地区で15人、真穴地区で38人が利用し、保護者の評判も高いという。
同市が元保育士や社会福祉協議会などと協力し、地元公民館や小学校で預かる。本年度も両地区で開校を予定する。同市子育て支援課は「農家を支えられるよう続けていきたい」と力を込めた。
<取材後記>
取材のきっかけは、今回取り上げた広島県の矢野さんだ。初めて取材で知り合ったのが昨冬。農作業や4人の子育てに加え、くず米を使った離乳食、幼児食も開発する力強い姿に感銘を受けた。記者以上に時間がないはずなのに、笑顔あふれる表情でいつも対応してくれる。
取材を通じて、農業と子育てともに自分一人で抱え込まずに助けを求めることが重要だと感じた。矢野さんが言っていたように完璧を求めず、自分のペースで取り組むことが両立に近づく第一歩になるのかと思う。
記者は3年前に広島へ転勤して以降、数多くの子育て世代の農家に出会ってきた。両方とも忙しい中で取材を快諾してくれ、全力で応えてくれる。そんな農家に頭が下がる思いだ。
(西野大暉)

 Line
Line















