ダラムシャラのチベット人学校で数学と化学を教える女性教師、テンジン・ハドゥンさん(33)とドルマ・セリングさん(32)は亡命3世。互いの両親もインド生まれだが、子どもの頃、食卓にはチベットの料理やデザートが並ぶ家庭だった。
「そのせいか、授業でもチベット料理のことをよく話します。給食にも出るから、生徒も楽しそうに聞いてくれる」とセリングさん。ハドゥンさんも「伝統の文化や料理を教科の話題に取り入れるよう工夫しています」。

インドやネパールに約10万人が暮らすチベット人社会は、亡命時から「チベット人同士の結婚」が推奨されてきた。ダライ・ラマ14世も自著の中で「僧侶としてほめられたことではないが」とした上で、「強固なコミュニティを築く」ため、「チベット人女性はできる限りチベット人男性と結婚するよう伝えた」と記している。
ハドゥンさんも同じ考えで、「チベット人は減っている。チベット人以外の男性と結婚すれば、その速度は上がってしまう。固有の民族であるために、チベット人同士で結婚すべきです」と言った。
一方、セリングさんはこう考える。「異なる国や民族の2人が結婚しても、それぞれの文化が消えるわけではない。私は夫となる人の文化を知り、夫は私の文化を知る。生まれた子どもは二つの文化を身につける。チベット文化は広がる」
2008年の暴動を機に、「高度の自治」を求めるチベットと中国との対話は暗礁に乗り上げ、帰還の道筋も見えない。この間、インドで世代交代が進み、亡命社会には多様な意見や議論が飛び交う。
全世代に共通するのは、民族の将来を思う熱量の大きさだ。
北京五輪を前に、中国・ラサで同年3月、チベットの独立を求めるデモが発生。中国政府は武力で鎮圧し、多くの犠牲者が出た。デモは中国国内の他、インドやネパール、日本、欧米など世界中に飛び火した。

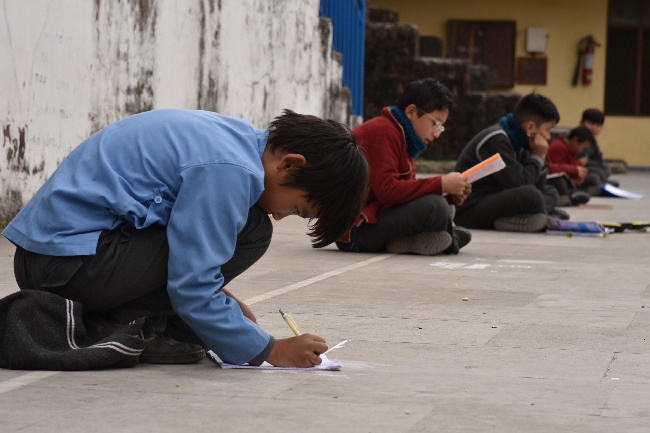

取材後記
年間の自殺者が2万人を超える日本。ノーベル平和賞受賞者のダライ・ラマ14世(89)はかつて、日本の現実に心を痛め、亡命先のインド・ダラムシャラで「(悩んだら)周囲に頼ろう」「隣人が苦しんでいる時こそ救いの手を差し伸べよう」と呼び掛けている。当時(2010年5月)の日本は自殺者が年間3万人を超え、世界から関心を集めていた。10年前から2万人台前半で推移しているが、先進7カ国の中で突出して多い状況は変わっていない。

自殺を考えたことがあるのでは、との記者の質問には「最高機密」と持ち前のユーモアで返し、一般論として「現代社会は人間への慈しみや愛が欠けている。次世代のため、内なる価値観を重視する教育システムが必要では」と問いかけた。
(栗田慎一)
 Line
Line















