栽培基準設け独自認証も
人や地域、環境などに配慮した消費行動を指す「エシカル消費」。持続可能な開発目標(SDGs)とも関連する。SDGsの制定から10年を迎え、エシカル消費が国内でどの程度、浸透しているか。どのような取り組みがあるか。今後の展望を探った。
「環境への負荷が少ない商品を購入する」「エコバッグやマイボトルを使う」「地産地消に取り組む」「食品ロス対策を実践する」などがエシカル消費。2015年の国連サミットで掲げられたSDGsの17項目のうち、「つくる責任、つかう責任」に関連する。消費者庁の24年度消費生活意識調査で「エシカル消費を知っている」と回答した人は27・4%にとどまった。
認知度に課題
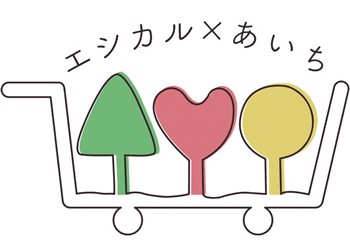
そこで消費者に近い場所で、認知度向上に取り組む愛知県庁を訪ねた。県は、内閣府の「SDGs未来都市」に選ばれたことを踏まえ、21年3月に特設サイト「エシカル×あいち」を開設している。
県民文化局県民生活部県民生活課の担当者は「認知度は十分とはいえず、まだ向上の余地がある」との認識を示す。県は、エシカル消費の推進で、小学生から大学生までを対象に講座を開くなど若者の啓発に力を入れる。農業との関係性では「地産地消をはじめ、被災地の農畜産物を積極的に購入するなどの『応援消費』を実践することが、農業を支えることにつながることを学生をはじめ広く県民の皆さんへ伝えている」と話す。
農業とエシカル消費を結び付けた事例の一つが、コープあいちだ。化学合成農薬や化学肥料の削減で農産物の栽培に基準を設け、独自の「栽培自慢」認証をつくる。組合員には、認証マークを付けた農産物を購入するよう呼びかける。地産地消の推進では、JAあいち知多と連携し、店舗に同JA産農産物の特設コーナーを設ける。コープの特別商品推進の吉田優樹課長は「エシカル消費の促進は、JAとの連携が欠かせない」と話す。
学生が試食会

若い世代の問題意識にも対応する。コープ日進店と名古屋学芸大学管理栄養学部は、同店で「野菜を食べよう試食交流会」を開いた。学生が農産物を活用したレシピや店内広告(POP)を作り、店頭で試食を提供した。コープ職員は「学生がやる気をもって取り組んだおかげで、店も活気づいた。学生からは、来店客との交流が楽しかったという前向きな意見が多かった」と成果を語る。
今後の推進には「若い人の積極的な参画が必要。組合員からの声を積極的に取り入れ、引き続き地道に活動を続けていく」と話す。
<取材後記>
取材を通してエシカル消費の重要性と、一層の認知拡大や実践の難しさを痛感した。
私自身、以前から言葉自体は知っていたものの、具体的にどのような消費を指すのかは理解できていなかった。スーパーでも、なるべく地元産野菜の購入を心がけてはいるが、つい価格重視で買い物をしてしまうことも多い。
まず必要なのは、エシカル消費が社会全体により浸透していくこと。そして一人一人が日々の買い物の中で、自分にできることを考えることが習慣化されることが大切と感じた。こうした積み重ねが地域や環境を守るだけでなく、生活者の心も豊かにしてくれると信じ、記者も積極的に取り組もうと思う。
(小室駿)

 Line
Line















