三河島菜は江戸東京野菜の一つで、江戸時代には荒川区三河島で相当作られていたようです。しかし、ハクサイの普及などで次第に作付けが減り、昭和初期には絶滅してしまいました。ところが、その前に仙台藩の足軽によって種が持ち出され仙台芭蕉菜として受け継がれていたことが分かり、荒川区に“逆輸入”されて三河島菜として復活したそうです。小さなうちは菜っ葉状態でも収穫できますが、本来は野沢菜のように葉を数十センチまで大きく育て漬物として利用されていたのです。葉は明るい黄緑色です。

実際に、三河島菜もナミハナアブで授粉させた時には途中で異株が出現したことがありました。母本を選抜し直して採種を続けてきました。アブラナ科の多くは自家不和合性なので、採種株は1株でなく複数用意します。また、固定種は純粋な系統に絞り込むと内婚弱性で弱くなるため、微妙に遺伝的に違った似たもの同士の集団である方が良いのです。
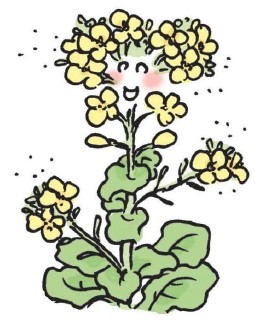
そこで蜂やアブに頼らず、人工授粉をすることを考えました。選んだ母本を蜂などが入ってこないトンネル内に植えます。4月にはアブラナ科の菜の花は次々と花が開きながら、上に向かって伸びてきます。その花に手のひらを当てると、手に黄色い花粉がいっぱい付きます。その手を別の株の花に当てて授粉し、また戻って別株の花粉も授粉させます。花が咲いている間、その作業を繰り返します。セイコー農園の活動日は週1回なので、授粉効率が上がるよう、毎日来られる地元在住の利枝子さんと成子さんに授粉をお願いしました。
花が終わり、花茎にはたくさんのさやが伸び中に種が入ります。株の緑色が抜けて枯れるころに刈り取って、防虫網に包んで雨の当たらないところで2週間ほど乾かします。乾いたらさやから種を脱粒します。ごみは扇風機で飛ばし種を精選します(愛菜家・福田俊)
動画が正しい表示でご覧になれない場合は下記をクリックしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=VU8yUiQ9quc
 Line
Line















