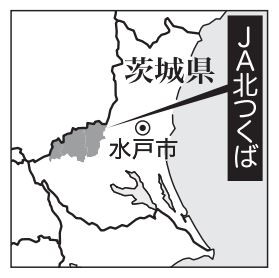
同部会は、65ヘクタールで約40万ケース(1ケース8キロ)を出荷する。量・額とも日本一を誇る鍵は、選果選別の徹底だ。「量が強みの産地。後は品質を良くすれば日本一が取れると考えた」と、大久保修一部会長は強調する。
出荷基準を徹底するためカラー見本を作成。年2回の目ぞろえ会は3カ所の集荷場合同で実施し、選果のばらつきをなくす。部会の検査委員会が抜き打ちの巡回検査も行う。出荷前には全生産者の全作型で試し割りを実施。糖度12を超えた同一作型の圃場(ほじょう)から出荷するよう徹底。試し割りの数は毎年1000個にも及ぶ。
初めから厳しい選果選別だったわけではない。部会発足の1998年当時に12億円あった販売額は、景気の低迷で2006年に6億円に激減。
転機となったのは13年、二番果以降も食味が良い品種「スウィートキッズ」の本格導入だ。「品種が良くても選果が伴わないと単価は上がらない」(同部会長)と選果を徹底した。結果、旧品種と比べ1ケース当たり最大で300円もの差が生まれ、部会員の意識が変わり出した。宣伝活動にも力を入れ、消費者と接したことも刺激になった。
翌年には1ケースの平均単価が初めて2000円を超えた。厳格な選果で秀品率こそ下がったが、優・良品の単価が向上。平均単価の底上げにつながった。卸売業者が「JA北つくばは良品でも質が高い」と新規顧客に推すほどだ。21年には新型コロナウイルス禍の巣ごもり需要で20年ぶりに販売額が10億円を超えた。
後継者も増えた。21年には45歳以下の生産者22人でつくる青年部も発足し、栽培マニュアル動画の作成などに取り組む。(長野郁絵)

V字回復の大きな要因が部会員の意識改革だ。そろいのピンバッジで一体感を高め、これまで「忙しい」と一蹴していた販促に赴き、消費者に選ばれる産地を目指してきた。部会員は、出荷基準をクリアしても「3日待てば糖度があと0・5上がる」と、より高い品質を求めるようになった。産地の誇りを育てることが大切だ。
概要
部会員数=144人(22年度)
販売額=10億3900万円(21年)
動画が正しい表示でご覧になれない場合は下記をクリックしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=tHt5MYlWL2Y
 Line
Line















