
2010年に3億円だった販売額は、20年に9億円に拡大した。増産を後押しするのが、20年に導入した自動選果機だ。運ばれたブロッコリーを保冷庫で一晩寝かせた後、自動選果機で等階級別に詰め、氷を満たして出荷する。これまでの選果機より処理能力が高まり、ピーク時は1日5000箱(1箱6キロ、約20個入り)を作る。部会長の藤田稔さん(55)は「全部会員が持ち込み、選果の労力軽減になっている」と話す。農家は生産に集中でき、規模拡大につながっている。
新規就農者も増え、部会が活気づく。30、40代が中心の「若手後継者会」は部会員の半数近い32人で構成、研修会などで栽培技術を磨く。20種以上の品種を試験栽培し、成果を部会内で共有。出荷増に向け次期の作付けや作型を先導する。こうした取り組みが19年、日本農業賞大賞と農林水産祭天皇杯の受賞を引き寄せた。
販売金額の確保に向け、スマート農業も活用する。国のスマート農業実証実験で営農支援アプリを導入、生産情報の見える化を進める。JA西部基幹営農センターの田中慶輔主任が各圃場(ほじょう)の播種(はしゅ)や生育状況などを記録。収穫日や出荷量を予測し、部会で共有する。市場にも情報提供し、相場の安定につなげる。田中主任は「需給の均衡を産地主導でつくるため、この取り組みを全国へ広げる必要がある」と強調する。
水田転作などによる生産量の増加で、相場が低迷して減産する産地もある中で、同部会は増産を堅持する。藤田部会長は「作型を調整し、冬期出荷を増やすことで、単価の回復と販売額10億円への到達を目指す」と意気込む。(柴田真希都)
部会長 藤田稔さん
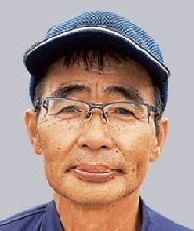
概要
部会員数=66人
生産規模=230ヘクタール・約2600トン(21年度見込み)
動画が正しい表示でご覧になれない場合は下記をクリックしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=b6eIZ0tjKxQ
 Line
Line















