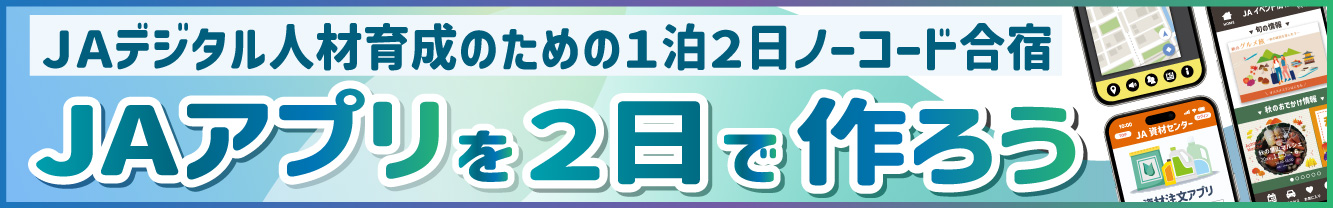[論説]中山間直払いの見直し 集落加算廃止 再考せよ
同加算措置は、第5期(20~24年度)に初めて設定され、営農以外の生活支援などに対して基礎部分に上乗せして交付される。23年度は全国で555協定(2万4586ヘクタール)で同加算を活用。過疎高齢化が進む農山村で、採算の厳しい小売店舗の経営や、配食、送迎サービス、営農ボランティアなど多様な活動を下支えしてきた。
同加算の廃止で、集落からは「店舗を継続できない」「(加算は)病院への送迎支援に欠かせない。廃止は地域の存続に深刻な影響をもたらす」などの声が相次ぐ。
廃止方針について、同省から有識者でつくる制度に関する第三者委員会に対して、事前の相談がなかったという。複数の委員は「加算の継続は当然だと思っていた」「唐突で納得できない」などと反発。同省は「第三者委員会に概算要求の内容まで諮っていない」と説明する。
だが、こうした手法は、改正食料・農業・農村基本法の第三章五十条で定める行政運営の「透明性の向上」に反しており、看過できない。
同加算は、地域の暮らしを住民主体で守り、多様な人材との交流の原資となっている。加算を活用する集落は一部だが、5期当初から広がりを見せる。さらに、次期の第6期対策で加算を生かした地域づくりを検討する集落の活動に水を差すことになる。必要なのは同加算の利用をいかに広げ、集落活動をどう守るか、といった視点のはずだ。
同省は「農村型地域運営組織(農村RMO)への移行や、自立した活動を検討してほしい。10月以降、丁寧に説明していきたい」(地域振興課)とする。しかし、複数の集落や小学校区単位で地域の暮らしを守る活動を進めるRMOと、直接支払いの集落は範囲や規模が異なる。農村RMO推進研究会の委員からは「移行は乱暴」との指摘が上がり、現場からも「農村RMOはハードルが高い」「地域が混乱する」との声が相次ぐ。
同省が今すべきことは、同加算の廃止方針の説明ではない。廃止に戸惑う現場の声や委員の指摘に耳を傾け、農業政策と農村政策を両輪で進める重要性を踏まえ、同加算の廃止を再考することだろう。
与野党代表選では、各候補が地方創生を重視する姿勢を打ち出す。同加算の廃止はそれに逆行しており、到底認められない。
 Line
Line