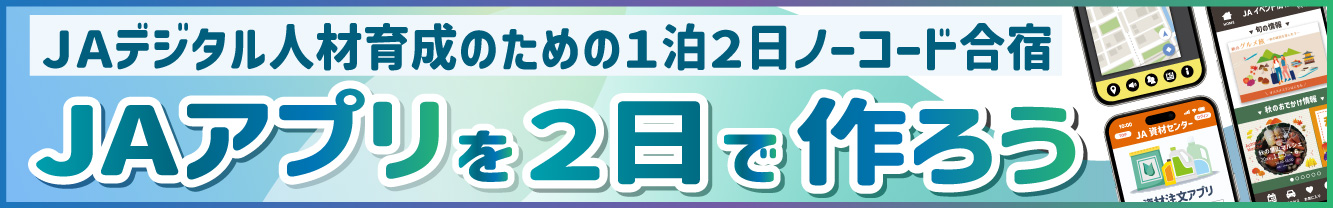[論説]都市農業の日 地方へ広がれ生産緑地
都市農業の歴史を整理する。かつて「宅地化すべきもの」とされた市街化区域内の農地は、都市農業振興基本法(2015年)と同計画(16年)によって、「あるべきもの」に転換。市街化区域内の農地保全を支えたのが生産緑地制度だ。30年間の営農継続を条件に固定資産税など税の優遇措置が設けられてきた。
三大都市圏(東京・大阪・名古屋圏)の市街化区域内農地の5割は生産緑地。8割の約1万ヘクタールが、最初の指定から30年を迎え、宅地などへの転用が可能となる、いわゆる「2022年問題」が試練となった。都市農地が一挙に放出されれば、都市農業は衰退し、不動産価格の下落を招くことから、政府は「特定生産緑地制度」を創設。30年経過後も10年ごとに更新すれば、税制優遇を継続できるようにした。JAの取り組みも功を奏し、9割が特定生産緑地へと移行した。
こうした措置に加え、後継者のいない農家が生産緑地を第三者に貸した場合でも、引き続き相続税の納税猶予を受けられるようにした。この都市農地貸借法により、10都府県101市区が活用する(今年3月末現在)。貸借面積は117ヘクタール、前年度比15%増で、市民農園や新規就農の受け皿となっている。他にも生産緑地地区の面積要件引き下げや直売所設置を可能にする建築規制の緩和など、都市農地の利活用に向けた環境は整ってきた。
課題は、地方都市で生産緑地の普及が進まない点だ。制度を導入したのは昨年末時点で全国15都市にとどまる。国交省は「都市農地の保全は地方都市の喫緊の課題」と指摘する。農業収益の大半が固定資産税などに消え、このままでは「営農継続が困難になる恐れがある」として、生産緑地導入を促す。導入により固定資産税は、地方都市平均の50分の1になると試算する。
豪雨被害の教訓から、農地の持つ雨水の貯留機能などに着目し、生産緑地制度を導入したのは福岡県久留米市。同市は生産基盤と都市農地の多面的機能を保全しようと、都市計画に生産緑地を位置付けた。地方都市の貴重な農地保全は、地域の振興や食料安保の確保に貢献する。
新鮮な農産物の供給、食育や生消交流の場、防災・減災機能など都市農業の価値を再認識し、住民と共に守り育てていこう。
 Line
Line