
17歳の時に引き揚げ船に乗って満州から帰国した埠頭は、舞鶴引揚記念館に残る資料から場所を知ることができた。海上保安庁の巡視船や大型フェリーが着岸し、当時の面影はなかったが、「海の青さと、山の深い緑は、当時のまま」だった。
村尾さんは、記憶をたどるように港を見回しながら、あの日の軍国少年の姿を探した。
1945年8月15日。東京農業大学専門部農業拓殖科1年の村尾さんは、学友や満州開拓移民と共に、日本から1200キロ離れた満州東部のぬかるむ山中を逃げていた。敗戦を告げる玉音放送を知るよしもなく、「なぜこんなことになったのか」分からないまま、負傷した足の痛みをこらえ、懸命に歩いた。
戦時下の特例措置で中学校(5年制)を16歳で卒業し、4月1日に同科に入学した10日後、ソ連国境の近くに同大が設置した「満州報国農場」へ開拓実習生として送られた。「7000ヘクタールの草原を農地に変え、食糧難の本土を救う」とされ、村尾さんを含む新入生中心の96人は燃えた。
日本は既に制空・制海権を失い、本土空襲が激化していた。満州国では開拓移民の成人男子が召集され、農業経営も困難になっていた。だが、戦況や大陸の状況は国民に隠され、村尾さんも「日本の勝利」を信じた。
「幻想」は4カ月後に破られた。米国が長崎に原爆を投下した翌8月9日、ソ連が満州に進攻した。開拓村からの急報を受け、数日分の食料を馬車に積み、完達山脈へ逃げた。
中国東北部は1年分の雨が夏に降る。土砂降りの中、村尾さんの足袋は脱げてなくなり、けがで腫れた足裏は指の付け根が分からなくなっていた。
一家の主が兵役に取られた開拓村は、高齢者や女性、子どもが残されていた。逃避行中、多くが歩けなくなり、乳飲み子を背負った女性から「ひと思いに鉄砲で楽にしてください」と懇願された。
わが身を守ることで精いっぱいだった16歳の少年は、何もできず、通り過ぎた。

村尾孝さんら16、17歳の満州報国農場開拓実習生と開拓移民との逃避行は、夜間が中心で、日中はくぼ地に身を隠した。ソ連軍機に見つかれば、機銃掃射で「ミシンがけされた」。
農場から持ち出した食料はあっという間に底を突いた。
山中には中国人の畑が点在していた。8月は年1度の収穫期で、トウモロコシやニンジンが実っていた。村尾さんたちは盗み、野菜くずも拾って食べた。被害に遭った中国の農民に思いをはせたのは、帰国後におなかいっぱい食べることができた後のことだ。
逃避行から1週間が過ぎた頃、銃撃に代わって空からチラシが降ってきた。「戦いは終わった。山から降りてソ連軍に武器を引き渡せ」と日本語で書かれていたが、誰もが信じないように振る舞った。村尾さんも、敵の偽装工作だと口にすることで、思考を止めた。
だが、無人となった日本の軍施設を通りかかった時、機銃掃射を受けたトラックに牛缶やさば缶が大量に残っていた。日本にいてもめったに口にできないごちそう。「ある所にはあるんだな」。分け合って食べていた誰かの一言は、鉛のように腹の底に沈み、疑念となって居座り続けた。
9月7日、現在の黒竜江省横道河子の山中で関東軍司令部の将校に出くわした。将校が読み上げた「終戦の詔勅」で、ようやく敗戦を知った。悔しさも悲しさも感じなかった。ただ、家に帰れることがうれしかった。
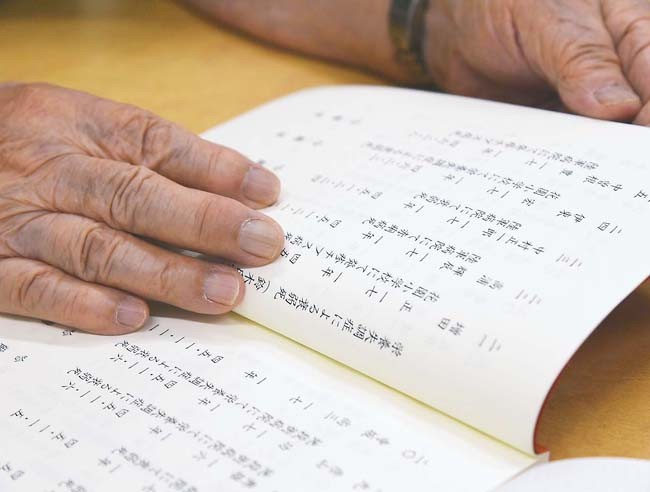

逃避行中、96人のうち5人が亡くなっていた。村尾さんら91人も、すぐには帰国できず、日本人収容所になっていたハルビンの花園小学校などに送られた。劣悪な衛生環境の中、零下20度の酷寒と栄養失調、赤痢などで53人が死んでいった。村尾さんは、凍った友の遺体を直径10メートルの墓穴に運び、無数の遺体の上に重ねた。腐敗が始まる雪解けの春になって土をかぶせた。
「山、岩、木はここにあるのに、人間は殺し合い、銃弾一つでいなくなる。地球にとって人間は必要なのか。いることで問題が起きているのではないか」。村尾さんは夜、満天の星空に問うた。
46年夏、米軍が用意した引き揚げ船に乗った。幾多の無念を思うと、枯れたはずの涙があふれた。
水平線から大山(鳥取県)の山容が見えた時、寒冷・半乾燥地帯の満州にはない緑一色の大地に感動した。舞鶴(京都府)に入港した時、照葉樹の深緑に目を見張り、なぜか、「日本は大丈夫だ」と確信した。「農業を立て直したい」と思った。
(栗田慎一が担当します)
 Line
Line















