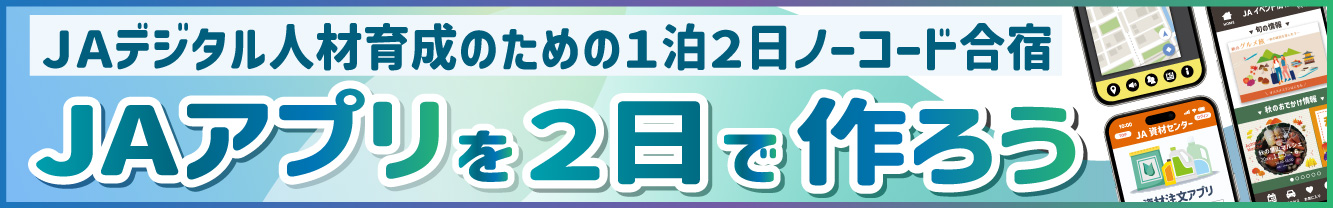母自身は戦前・戦中の世代で、しゃれた料理はあまり食べたことはなかったと思うんですけど、当時出始めていた料理本を買ってきて勉強し手をかけていました。カレーならスパイスを工夫していましたし、春巻きなどは皮から作っていました。

他の子たちはおいしくないと文句を言ってたみたいですけど、私はものすごく好きで、休んだ子がいるとお代わりをしていました。4時間目が終わって給食なのに、間違って3時間目が終わった後に給食の用意をしてしまい、皆にばかにされたこともあります。
給食の女王というあだ名を付けられ、「今日は休みの人がいるから、給食の女王が食べれば」と言われて食べたりしていたんですね。
それが母の知るところになって。母は恥ずかしく感じたようです。
自分でパンを焼き、ジャムも手作りする母は、給食は何か体によくないものが使われていると思っていたんですね。たとえばジャムは水あめみたいなものが入っている、と。また給食では時々粉末が出され、それを牛乳に加えるとココア味になりました。甘くてなんともいえないおいしさを感じたんですが、糖分控えめのお菓子を作っていた母にとってみれば、それはよくない甘さ。
私は、母が眉をひそめればひそめるほど給食に対しての思い入れが強くなり、「自分は一生懸命やっているのに」と思う母に、粗野なことを言ったりしていました。

母は、料理を作って食べさせるということに、ものすごく固執していたのです。やがて年を取り、病気をしたりで体力が落ちてきました。すると、私が「来週、週末に帰るね」と連絡すると、「ご飯を作ってあげられないから、来ないで」と言うようになったんです。
こっちにすれば「何を言ってるの。作れないから行くんじゃないの」という気持ちなんです。私はそんなに料理は上手ではありませんけど、ちょっとしたものは用意できます。あるいは買って行ったりとか。

ですから大げさにいうと、「料理を作れない=自分の存在価値がない。子どもにも会えない」というように感じたんだと思います。
何度となく、その件について話をしました。私は母に、料理ができないなんて大したことじゃないと言ってあげたいのですが、それを言ってしまうと、一生懸命家族に料理を作ることを自分のよすがとしていた母の生き方を、否定するみたいに受け止められてしまいます。
私は、夫や子どもにおいしい料理を作ってあげる生き方はしませんでした。母は「あなたは自由にしていいのよ」と言ってくれましたが、実際のところはどう思っていたのでしょう。わずか1世代違うだけなのに、女性の生き方にはこれだけ違いがあるのですね。
(聞き手・菊地武顕)
かやま・りか 1960年、北海道生まれ。東京医科大学卒業後、精神科医に。臨床のかたわら帝塚山学院大学教授、立教大学教授などを歴任し、著書も多数。2022年4月から、北海道のむかわ町国民健康保険穂別診療所でへき地医療に取り組む。週末の東京での精神科医としての臨床は継続中で、2拠点生活を楽しむ日々を送る。最新刊は「精神科医はへき地医療で“使いもの”になるのか?」(星和書店)。
 Line
Line