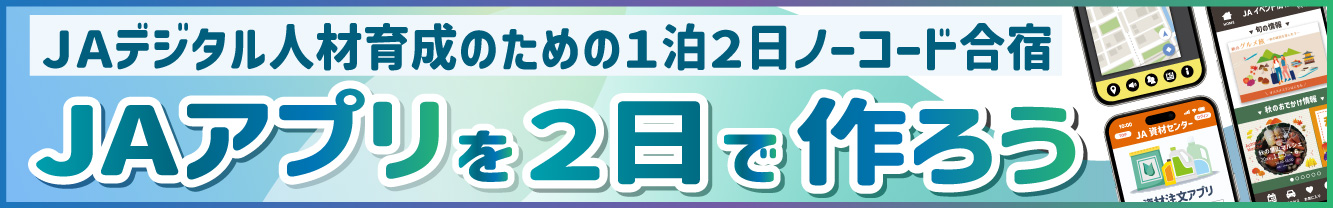終戦から79年 都市部の食料難に学ぶ 農村買い出し、物々交換も
「食べるためみんな必死」
東京都江東区の深川で生まれ育ち、終戦当時7歳だった上原淳子さん(86)は戦時中、アワや、汁に米が数粒浮かぶ雑炊などの代用食で飢えをしのいだ。終戦後もこんにゃくなどを食べていたといい、「しばらくは米をきちんと食べた覚えがない」と話す。
上原さんは東京・銀座や新橋の闇市などで、多くの人が食料を求める光景を目にした。
すしに添える海藻「うご」(オゴノリ)を売りに行った親戚に客が殺到し、数分で完売したことを、よく覚えているという。「うごでも腹に入れば良い、口に入るものなら何でも良かった。いかに終戦後の東京に食べ物がなかったか」と振り返る。
終戦当時15歳で、東京都文京区の根津に生まれ育った小林暢雄さん(94)は、農家とのつながりがない東京の友人に付き添い、埼玉の農村に買い出しに行く経験をした。面識のない農家に飛び込み訪問し、断られることもあったが、サツマイモや小麦などの代用食を中心に、持参した着物や時計などと物々交換できたという。
小林さんは「食べるためにみんな必死だった」と当時を説明する。
農業も疲弊させた戦争
太平洋戦争は人手や資材を不足させ、農業を疲弊させた。農水省の作物統計によると、主食となる米の生産量は終戦を迎えた1945年に582万トンと、戦争が始まった41年の7割の水準まで落ち込んだ。国立博物館の昭和館(東京都千代田区)の資料によると、配給は遅配や欠配が続き、多くの都市住民が食料を求めて闇市や農村に押し寄せたという。
平時から連携必要
宮城大学食産業学群の森田明教授は、終戦後の都市部の食料難について、流通インフラの崩壊や、強制供出の停止で都市への食料供給が滞り、利益が見込める闇市に食料が流れたことなどが要因とみる。一方で、現在ほど都市と農村の分断がなく、農村と関係を持つ一定数の都市住民は食料を確保できていたと推測する。
森田教授は「非常時に農村と都市の連携が必要になることは明らか。当時の食料難から学べる教訓だ」と指摘。消費地が非常時でも必要な食料を確保していく上で、農村と積極的にコミュニケーションを取り、良好な関係を構築していくことが大切だと提起する。
(菅田一英)
 Line
Line