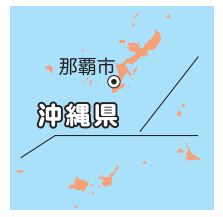
琉球料理保存協会で副理事長を務める松本嘉代子さん(83)は「まろやかな甘味が食欲をそそる。ご飯が進む夏ばて知らずの料理だ」と話す。
ナスに似た食感
ヘチマは、たわしなど日用品として使われるイメージがあるが、同県では直売所やスーパーで簡単に手に入る食材だ。ヘチマの果肉は、少しぬめりがあって柔らかく、食感はナスに似ている。ビタミンやミネラルも豊富だ。沖縄本島ではナーベーラーだが、宮古島では「ナビャーラ」、八重山地区では「ナベーラ」とも呼ばれる。
ナーベーラーンブシーの「ンブシー」は、煮汁の出やすい食材を使ったみそ煮を指す。ナーベーラーンブシーは、ヘチマのみそ煮という意味になる。島豆腐と豚肉も一緒に煮込むので、タンパク質やビタミンを効率よく摂取できる栄養満点の料理だ。
料理には、青々しく柔らかいヘチマを使う。ほんのりとした甘味となめらかな口当たりが癖になる一品。種も柔らかく、食感のアクセントになるため、取り除かずそのまま調理するのが一般的だ。
中火でじっくり
味付けは、だし汁と白みそだけとシンプルだが、だし汁が食材と混ざり合って、「アジクーター(濃厚な味)になる」と松本さんは話す。
ヘチマは、火を通すと粘りのあるとろっとした甘い汁が出る。この汁のうま味が料理をよりおいしく仕上げる。松本さんは「中火でじっくりと、焦げ付かないように煮ることが汁を適度に出すこつ」と説明する。
レシピ
■材料(5人分)
ヘチマ900グラム、豚バラブロック肉80グラム、油大2、島豆腐3分の1丁、だし汁50ミリリットル、白みそ大3~5、かつお節少量。
■作り方
①ヘチマは皮をこそげ取り、厚めの斜め切りにする
②豚肉をゆでて、1センチ幅の短冊に切る
③島豆腐は軽く水分を取り、手で適当な大きさにほぐす
④だし汁で白みそを溶く
⑤鍋で油を熱し、②を入れて強火で炒める。脂が溶け出てきたら①を加えて強火で炒め、軟らかくなったら③と④、かつお節を入れる
⑥中火でしばらく煮る。ヘチマから汁が出て、とろみがついたら皿に盛る
動画が正しい表示でご覧になれない場合は下記をクリックしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=n6n2omjhsUE
<食材ヒストリー> ヘチマ 開花2週間が食べ頃

県で栽培されるヘチマは在来品種で、農家が種子を自家採種し、現代まで脈々と引き継いでいる。
ヘチマは、開花してから2週間後の若い実を収穫する。成長し過ぎると繊維が強く、ヘチマ特有の滑らかな食感が失われてしまうためだ。おいしいヘチマの見分け方は、長さが20~25センチほどで太過ぎず、表面がきれいな緑色のものを選ぶことだという。
 Line
Line















