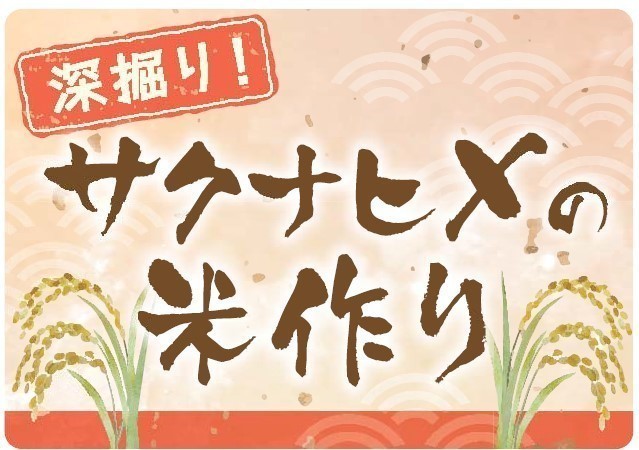 稲作を取り入れた人気ゲームが原作のアニメ「天穂のサクナヒメ」とのコラボレーション企画「深掘り!サクナヒメの米作り」。第6話「恨みの炎」で、主人公「サクナヒメ」と仲間たちは、ついに米の収穫にこぎ着けました。ただ、刈り取りに乾燥、脱穀、もみすりと仕上げの工程も全て手作業。苦労を乗り越え、念願の米を口にしたサクナヒメたちの表情は…。
稲作を取り入れた人気ゲームが原作のアニメ「天穂のサクナヒメ」とのコラボレーション企画「深掘り!サクナヒメの米作り」。第6話「恨みの炎」で、主人公「サクナヒメ」と仲間たちは、ついに米の収穫にこぎ着けました。ただ、刈り取りに乾燥、脱穀、もみすりと仕上げの工程も全て手作業。苦労を乗り越え、念願の米を口にしたサクナヒメたちの表情は…。
◇
「実っとるぞ。実っとる」。サクナヒメは家の田に広がる黄金色の稲穂を見て、喜びの声を上げます。そっと稲穂に手を触れ「うむ。びっしりつまっておるの」と満足げです。仲間の一人で、サクナヒメの稲作を手伝ってきた田右衛門は「まだ油断は禁物にござりまするぞ」と忠告します。「秋は大水や嵐も多い季節。時には一晩で倒れてしまうことも」と心配します。
現実の稲作も天候に大きく影響を受けます。地球温暖化を背景に近年、ゲリラ豪雨や台風などの発生回数が増え、収穫間近の水稲が倒伏するなどの被害が続発しています。
今年もすでに水害が発生しています。米どころ秋田、山形両県では7月に大雨が降った影響で、水稲にも被害が出ました。水田に土砂が流れ込み、収穫できなくなるケースも発生しています。
サクナヒメも災害が不安になり「そんなことになったらどうする?」と尋ねます。田右衛門は「また来年、一から作り直しにござりまする」と、基本的に一年間に一度しか収穫できない稲作の厳しさを改めて説明します。
「そんな…」と落胆するサクナヒメ。育て役の「タマ爺」は「それが稲作でございます。それゆえ収穫の喜びもひとしお」と話します。
サクナヒメたちの田はついに収穫を迎えます。現実の稲作のように、機械のコンバインを使って収穫することはできないので、稲刈りは手作業です。サクナヒメは鎌を手に、一株ずつ丁寧に刈り取ります。長時間腰を曲げたままの作業に「これはまた腰にくるのう」と収穫の大変さを実感します。
現実の稲作では、コンバインで刈り取って脱穀後、乾燥施設に運び込みます。乾燥作業は重要な工程の一つとされています。米づくりが盛んな宮城県は「収穫した生もみを放置すると、発熱して変質米の原因となる」(みやぎ米推進課)として、刈り取り後は速やかに乾燥作業に入るよう促しています。
ですが、サクナヒメたちの回りに稲を乾燥させる設備なんてありません。稲刈り同様、乾燥も手作業です。田右衛門はサクナヒメの前で、稲を天日に当てて乾燥させる「はさがけ」をやって見せます。刈り取った稲を束にまとめると、竹を使って田の中に組み上げた稲架にかけて干していきます。

はさがけは一定期間、天日に干して稲をじっくりと乾かし、風にも当たるので乾燥むらができにくい利点があります。半面、乾燥に時間がかかり、天候の影響も受けやすいという課題があります。
現実の稲作でも、消費者に昔ながらの農作業を体験してもらう一環で、はさがけを取り入れていることがありますが、基本的には、まとまった量を効率よく乾燥させるため機械を使うのが主流です。
稲をむらなく乾燥させる方法として、宮城県は「二段乾燥」を挙げます。田が乾燥し切っておらず、一定量の水分を含んだ状態で収穫した稲を急激に乾燥させると、胴割米などが発生する恐れもあります。これを避けるため「二段乾燥」は最初の乾燥後、もみの水分が一定程度になったら中断して風を通し、最後に仕上げ乾燥をします。宮城県は「米の品質を維持した上で、一定の時間内でまとまった量を乾燥できる」(同課)と話します。機械作業であっても、現実の米産地でも手間をかけて米を仕上げています。
稲が乾いたら、次は稲穂からもみを取る「脱穀」です。こちらも現実の稲作では、コンバインが稲刈りと同時に済ませますが、サクナヒメは手作業です。
田右衛門は、竹に割れ目を入れて作った「こきばし」を使って脱穀をやって見せます。竹の割れ目に稲穂をはさんで引くと、もみが取れていきます。サクナヒメは、もみを手にして「これぞワシがよく目にしていた米」と喜びますが、作業はまだ終わっていません。

田右衛門から説明を受けたサクナヒメは「まだあるのか?」と驚きます。まずは、もみを臼に入れて杵ですり回します。「こんなことまで、しなくてはならんのか」と米作りの工程の多さを改めて実感します。
次は米つき。「精米」とも呼ばれる最後の工程です。サクナヒメは「こうか?」と田右衛門に尋ねながら、もみすりを終えた玄米を臼に入れ、木の棒で突いていきます。
現実の精米は、機械でやるのが主流です。精米機メーカー各社が公表している情報の中には、業務用の機種だと1時間で5トンの精米能力を持つ機種もあります。一般向けに、持ち込んだ玄米を精米してくれる「コイン精米機」だと、5分半程度で30キロを精米できる機種もあります。
一方、サクナヒメは量が限られているとは言え、手作業で米を突いて精米するため、時間がかかります。夜がふけても作業を続け、日が昇り始めた頃に、ようやく終わりました。最初は薄く色付いていた米粒は、真っ白になっていました。
数々の工程を終えて、自らの手で仕上げた白い米を前にしたサクナヒメは、両手で米をすくい上げ「きれいじゃのう」と見つめます。
現実の精米も、表面のぬかを取り除くという点は劇中と同じです。一般的に流通しているお米は、表面に「肌ぬか」と呼ばれるぬかが、かすかに残っていて、それを落とすため、研ぎ洗いをします。
研ぎ洗いすら必要ないのが「無洗米」です。全国無洗米協会によると、精米技術などが向上し、「肌ぬか」も取り除くことができるようになったため、無洗米が登場したそうです。豊穣神であるサクナヒメが腕を磨いていけば、いつか刈り取った米を無洗米にすることができるかもしれません。

その様子を見たタマ爺が語り始めます。田起こしから田植え、水管理など、これまでの米作りを振り返り「一時も離れず、成長を見守り、愛情を注ぎ育て、結実したものです」と話し、「それだけに米は強い。米は力なのです」と説きます。
タマ爺の言葉を聞いたサクナヒメは、目に涙を浮かべ、静かに笑い出します。やがて、みんなで「あはははは」と笑い、改めて収穫を喜ぶのでした。

テレビ放送の時間帯と放送局は次の通り。
▽毎週土曜日午後11時から=テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
▽毎週火曜日午後9時半から=AT-X
▽毎週金曜日午前1時29分から=熊本県民テレビ
▽9月2日から毎週月曜日午前2時(毎週2話ずつ、最終回のみ1話)=富山テレビ放送
各種動画配信サービスでも配信されている。
(C)えーでるわいす/「天穂のサクナヒメ」製作委員会
 Line
Line















