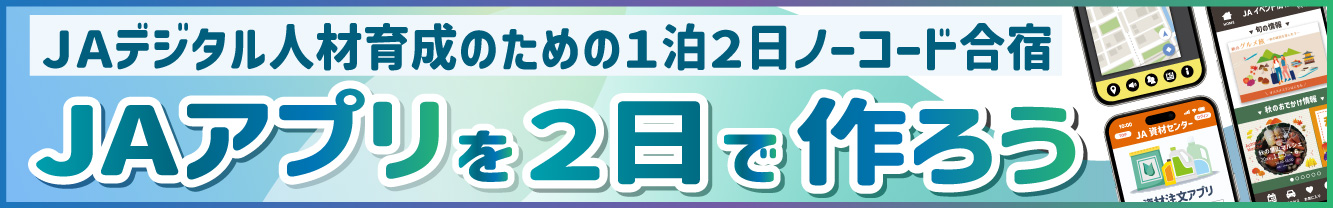[論説]悪化する出産環境 少子化対策と両輪が鍵
政府は、2030年代の若年人口は現在の倍のスピードで急減するとして、子育て政策を進める。だが少子化の進展以上に、分娩できる施設は激減している。厚生労働省によると、1996年に3991あった分娩取り扱い病院・診療所数は、2020年には全国で2070と、25年間で半減した。出生数の減少以上に安心して産める施設は減少している。こうした傾向は、特に地方ほど顕著だ。
出産に昼夜は関係ない。そのため、産婦人科の医師は勤務外の時間も、病院にすぐに駆けつけられる場所にいなければならないなど、生活に制約がある。JAの病院で1人体制で産婦人科を担当してきた医師は「いつ、なんどき呼ばれるか分からず、予定を極力入れられなかった」と明かす。訴訟リスクもあることから、産科医のなり手は他の診療科に比べて少なく、学会などへ出張に行くことも難しかったという。こうした背景から、JA香川厚生連屋島総合病院など、複数の病院が分娩休止を余儀なくされている。
訴訟リスクや過酷な勤務状況などから、勤務医の産科離れは長年の課題だった。医学生・研修医の優遇策や離職した女性医師の復帰支援など対策が取られてきたが、解決に至っていない。それどころか、出生数の減少や本年度から始まった医師の働き方改革などで地域での産科医療は“綱渡り”の状況だ。現場での対応は限界にきていることは明白だ。政府が少子化を憂うのであれば、まずは地方での産科医不足や環境整備に全力を上げるべきだ。
産科を都市に集約することも進められているが、地方都市ですら産科を維持することができなくなっている。産科をいったん失ってしまえば、地域にとっても死活問題になるという指摘もある。
政府は、少子化対策への支援を強調しておきながら、安心して産める環境を整えず、悪化させている。この責任は重い。当直明け勤務の減免、勤務条件の改善、医師の意欲を上げるための施策など仕組みづくりが急務だ。産科医療だけでなく、地方医療を支える多くの厚生連病院では、人口減少やコロナ禍による受診行動の変化などで患者数が減少し、収支は悪化している。財政支援を強く求めたい。
医療は地域の基盤だ。産科整備は、子育て支援と両輪で進める必要がある。
 Line
Line