自由化の「代償」重く 鈴木氏
司会(本紙論説委員・緒方大造) ウクライナの現状を、どう受け止めているのか。
平澤氏 過去の食料危機と様相が違う。1973年は不作、2008年はバイオ燃料の拡大が要因だった。今回は戦争や経済制裁で意識的に輸出を止め、その結果1000万人単位で飢餓に陥るというかつてない事態だ。
鈴木氏 自由貿易が大事だと言っていても、それが機能しなくなるという事態が起こる。アフリカなどウクライナからの輸出に頼っている地域が飢餓に陥る、という議論が起こっているが、日本も人ごとではない。
二村氏 一国の労働、生産はもちろん、経済的、文化的交流も含め各国とのつながり、協調も大きく損なわれた。生命や暮らしが脅かされる事態に、生協も抗議声明を出した。戦前の状態に戻す意志を捨ててはならない。
司会 海外で食料安保の議論はどうなっているか。
平澤氏 欧州連合(EU)は80、90年代、生産過剰や冷戦終結で食料安保に対する危機感は遠のいていたが、中国からの輸入増、バイオ燃料への関心を背景に2000年代から急激に意識が高まった。EUは来年から始まる政策でも「食料安保第一」を目標に掲げる。生産維持に向けて、EU全域で所得を補填(ほてん)する直接支払いが柱だ。輸入依存の脱却へ、肥料・飼料の使用を減らす動きもある。EUが強く推進してきた環境保全型農業とも親和性が高い。
“環境”軸に施策再考 平澤氏
司会 日本も既存のサプライチェーン(供給網)を見直す時期に来ている。
二村氏 日本の農業は国際的にも安定した経済環境の下、効率重視で成り立ってきた。今回の事態でその環境が変わってしまった。地域資源の循環や肥料・飼料の国内製造など、今まで非効率とされてきた取り組みに光が当たるのではないか。みどりの食料システム戦略で掲げられている具体策も改めて優先度を考える必要がある。
司会 持続的な農業の再現には政策転換も選択肢となるのか。
鈴木氏 規制緩和や関税撤廃を続けてきた日本は、食料調達を輸入に依存するようになった。しかし、今や「お金を出しても買えない」状況だ。世界的有事で、日本も飢餓に直面するかもしれない時に、国内生産をつぶしている場合ではない。EUの直接支払いのような支援策を導入すべきだ。日本では、牛乳や米の過剰も課題に挙がる一方で、米国やカナダなどは価格水準に応じて政府が在庫を持ち、国内外の援助に回す仕組みを持っている。政府が需給の最終調整を担って、農家に安心を醸成し、有事の備えにつなげている。
平澤氏 肥料・飼料に関して言えば、みどり戦略の中で環境対策として位置付けてできる政策はかなりある。食料安全保障も加わり、耕畜連携を本格的に進める仕組みを考える好機だ。また、日本の土地利用型農業も本気で立て直さないと、生産基盤が危うくなっている。農地が足りない半面ずっと米が余っている現象が半世紀も続いていることに対し、全体を再設計して施策を打つ必要がある。
消費者も支える主体 二村氏
司会 食料の値上げは家計を直撃する。半面、価格転嫁しなければ農家は経営が立ち行かない。
二村氏 食料に限らずエネルギー価格も上がり家計に影響が出ている。コロナ禍で格差や生活困窮も深刻化し、生活を保障する社会政策が求められている。値上げを単純にコスト上昇分の転嫁という生産者と消費者の問題にすべきではない。生産者を支えつつ、消費者が暮らしに合わせて消費できる方法を社会全体で考える必要がある。
鈴木氏 輸入小麦の価格が上がればパスタやパンの価格も上がるのに、国内の作物で生産コストが上がってもすぐに価格に反映できない。これでは危機に耐えられる生産基盤の維持は難しい。政府だけに頼らず、実需者も国産を支えていく必要がある。学校給食に国産の安全・安心な農産物を使ってもらうなど、いろいろなアイデアを話し合ってもらいたい。
平澤氏 所得も下がり、景気も悪い中、消費者に「高い」といわれるものを買ってもらうのは、難しいのが現実だ。日本全体で食料を量的にカバーするなら、やはり、きちんと政策で手当てすべきだ。食料安全保障のためにどのような施策をどれだけの規模で打つかを決める際は、広範な国民の合意が必要になる。
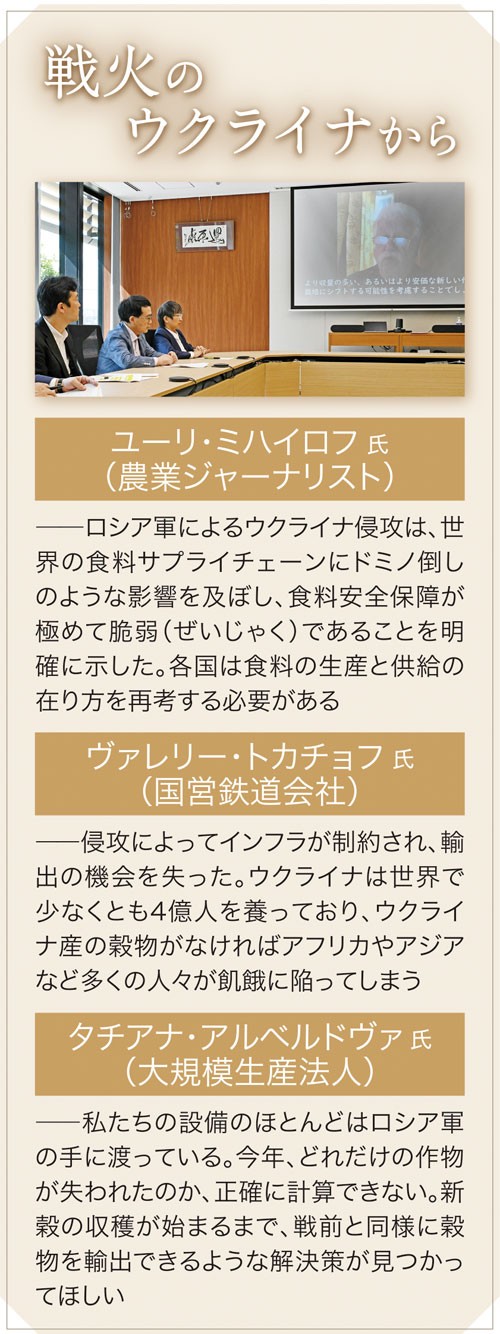
動画が正しい表示でご覧になれない場合は下記をクリックしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=Vihm9PB5ZrU
 Line
Line















