
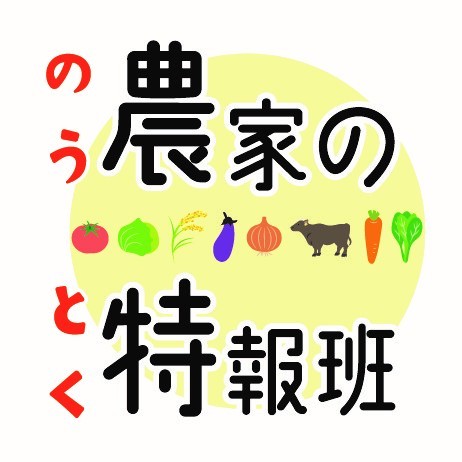
山形県酒田市出身の男性会社員(34)から本紙「農家の特報班」に投稿が寄せられた。
はんこたんな――。同県庄内地方に伝わり、農作業時の日よけのため、女性が顔を覆う藍染めの布のことだ。投稿者は現在、県外に住んでいるという。「子どもの頃は、はんこたんな姿が怖かったが、今は懐かしい。使っている人がいれば、思いを知りたい」
記者は手掛かりを求め、県と、庄内地方の2大都市・酒田市と鶴岡市に問い合わせた。だが一様に「使っている人はいないのでは」との答えが返ってきた。
次に頼ったのが庄内地方にある五つのJA。しかし、鶴岡市に本所があるJA庄内たがわのある職員は「平成初期までは見たけど……」という。もう30年前だ。

同町に問い合わせると、1週間後に返答があった。「職員の母親が使っているようだ」。電話すると、明るい声の女性が出た。「今日も使ってるよ」
見渡す限りの水田が広がる遊佐町――。水稲7ヘクタールを手がける池田律さん(70)宅を訪ねると、農業倉庫からにぎやかな女性の笑い声が聞こえてきた。記者がのぞくと、6人の女性が、はんこたんなで隠した顔を一斉に向けた。まるで、くノ一。思わず声を上げそうになる迫力だ。
6人は64~72歳。池田さんは20歳の時、嫁入り道具として、母親からはんこたんなを持たされた。虫よけや汗を吸う機能もあり、「他の日よけも試したけど、一番しっくりくる。習慣だな」。
はんこたんなには、花の刺しゅうがある。土門ゆきみさん(70)は「刺しゅうや下に巻く手拭いで、めんこくするのさ。畑でも気分を上げたくて」と教えてくれた。
しかし、6人は同町ではんこたんなを使う「最後の世代」だ。高橋紀久井さん(72)は「はんこたんなは自分の一部。死ぬまで着けると思う」と話すが、6人の他に使う人は1人しか知らないという。なぜ、使われなくなってしまったのか。
謎を解くため、記者は、6人に教えてもらった衣料店「カスリヤ」に向かった。町で唯一、はんこたんなを売っているという。店主は86歳の女性。きっと、はんこたんなの“生き字引”だ。しかし事前に電話をすると「今、店にある5本で販売終了」。
思いも寄らない展開になった。
酒田市立資料館によると、はんこたんなは庄内地方の方言で「半分の帯」という意味。秋田、新潟の日本海沿いの一部でも見られる。1913年の絵はがきの写真に、はんこたんな姿の女性が映っており、長南秀美調査員は「少なくとも大正時代には使われていたと考えられる」という。
「農家の特報班」(略称のうとく)に取材してほしいことを、LINEでお知らせください。友だち登録はこちらから。公式ツイッターも随時更新中です。
 Line
Line















