サクナヒメたちが米を作る「ヒノエ島」の火山が噴火し、田んぼに大量の火山灰が降り積もります。さらに島に住む鬼たちが襲ってきて、家や納屋が焼き払われてしまいます。
サクナヒメはその様子に絶句し、島での暮らしや米作りをあきらめかけます。もともと住んでいた神々の都に戻ろうと舟に乗りますが、仲間と一緒に過ごした「この島での日々が好きじゃ」と、思い直します。仲間たちもサクナヒメと同じ気持ちで、全員で「またうまい米を作るぞ」と決意し、再起に動き出します。

サクナヒメは、灰の混じった田んぼの土を手に取り「べとべとしておるし、穂肥の減りが著しい。やはり灰まじりの雨のせいか」と思案します。その言葉を聞いたサクナヒメの友人で、発明を司る神「ココロワヒメ」は、「水を目いっぱい入れて田を起こせば、重い土は沈み、灰は水とともに流し出せるかも」と思い付きます。
田んぼに水を張り、ココロワヒメが考え出した方法をやってみると、灰が出水口から流れ出ていきます。灰の排出を加速させるため、サクナヒメたちは時間を進めるという不思議な力を持つ「うつろいの玉」を使います。サクナヒメは、田んぼに手を入れて土の状態を確かめると「元に戻ってきた気がするぞ」と期待を膨らませます。

劇中は火山灰による被害でしたが、現実の稲作でも、さまざまな自然災害に見舞われます。台風や豪雨による水害によって、田んぼそのものが崩れることも少なくありません。
農地の災害復旧は行政が主体となって費用を補助しながら進めます。ただ、サクナヒメたちが「うつろいの玉」を使ったように時間を加速させることはできず、農地の復旧には一定に時間がかかります。農水省は「原則3年間で完成」(防災課)と説明しています。ただ、河川や道路といった農地以外の部分でも、復旧工事が必要な場合などは、完成まで3年以上かかることも想定されます。
熊本県では2020年7月の豪雨によって、田畑1037件で被害が発生しました。県によると現時点で977件、全体の9割超で再び農業ができる状態になっています。また、熊本県では、田んぼの貯水機能を高めて洪水被害を抑えることを目的とした「田んぼダム」の取り組みも広がっています。

水害だけでなく、高温などの気候変動も稲作に影響を与えます。稲の栄養が不足するのを避けるため、出穂期に与える「穂肥」の回数を増やすなど、現場では、さまざまな工夫を重ねています。
高温対策は収穫を終えた後の田んぼの管理も重要になってきます。農水省が公開している「水稲の基本的な栽培技術」は、有機物が豊富な田んぼは「保水力や窒素供給力が増し、異常気象下での稲の生育や登熟を助ける」として、「収穫後の土づくり」を推奨しています。
土づくりの具体的な方法の一つに「堆肥の施用」が挙げられています。稲わら堆肥だと10アール当たり1~2トン、牛ふん堆肥は同1トン、豚ぷん堆肥で500キロ~1トンを目安としています。
「稲わらのすき込み」も有効としています。稲わらの腐熟を進め、さらに温室効果ガスのメタンの発生を抑えるため、秋の時期に、深さ5~10センチの所にすき込むことを薦めています。
高温下でも米の品質や収穫量を安定させるため、農家は栽培中だけでなく、収穫後も土づくりに努力を重ねています。サクナヒメたちの田んぼも灰を取り除いた後は、再び土づくりが必要になってくるかもしれません。
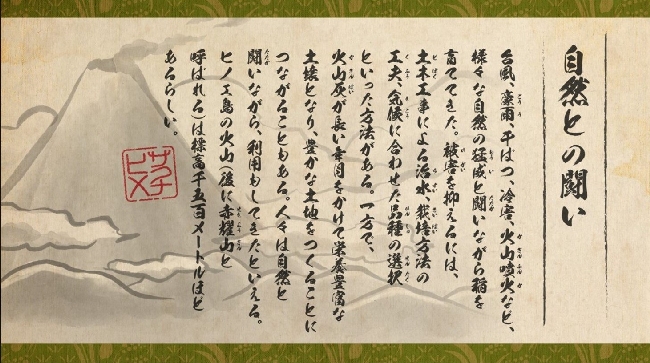
次回第11話は「赦しの光」。サクナヒメと仲間たちの田んぼは無事に再生し、かつてのように米作りができるようになるのでしょうか。
テレビ放送の時間帯と放送局は次の通り。
▽毎週土曜日午後11時から=テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
▽毎週火曜日午後9時半から=AT-X
▽毎週金曜日午前1時29分から=熊本県民テレビ
▽毎週月曜日午前2時(毎週2話ずつ、最終回のみ1話)=富山テレビ放送
各種動画配信サービスでも配信されている。
(C)えーでるわいす/「天穂のサクナヒメ」製作委員会
 Line
Line















